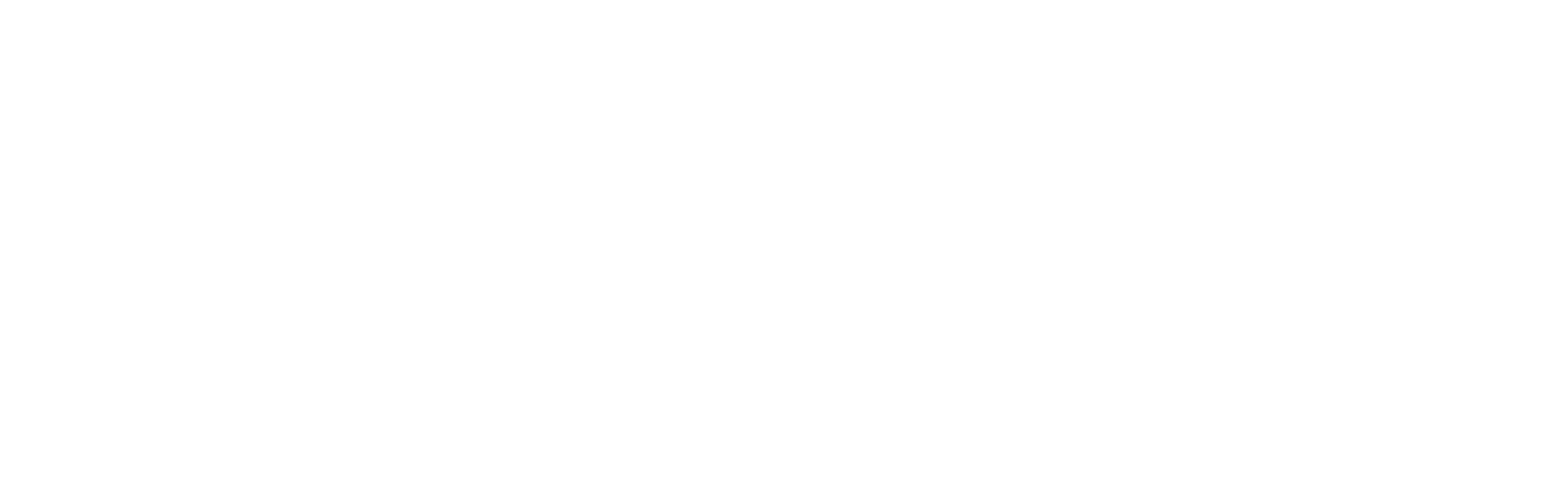とはいえ、難民キャンプでは離れた故郷を思い、また戦争を思い出しては辛い気持ちになる日々。国に帰れる日を夢見ながら、オーウンさんは一生懸命勉強しました。その努力が実を結び、彼は難民キャンプにある高校を卒業できたのです。
オーウンさんはこう語ります。
「難民キャンプに逃れた人たちは、お互いに支え合って暮らしていました。勉強が辛いとき同級生同士で助け合ったものでした。
学習を続けるため、励まし合い、助け合う人の存在があってこそ、高いモチベーションが生まれます。その難民キャンプでの経験を、いまの『カンボジア農村部の障害児のライフスキル向上プロジェクト』に活かしています」
ウクライナに平和と教育を
今春以来、ウクライナでの出来事は、世界中を悲しみと混乱の渦に巻き込んでいます。カンボジアでも、ガソリンや他の物の値段が上がるなど、人々の日常生活に影響を及ぼしています。
「いま戦争の中で生きる子どもたちのことを考えると、ポル・ポト時代の自分を思い出します。不安でおびえる毎日が、今すぐにでも終わりをつげ、平和が戻るよう願ってやみません」
自分の過去に重ね合わせながら、オーウンさんは祈っています。
ウクライナの子どもたちに、彼らに一刻も早い平穏と、しかるべき教育が行われる“スクール”が開かれることを…。